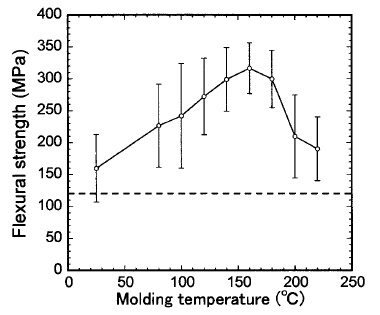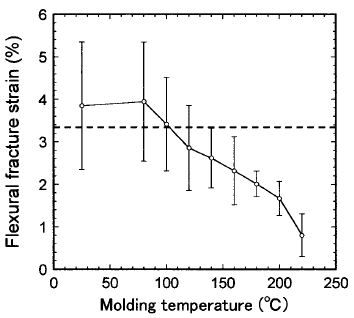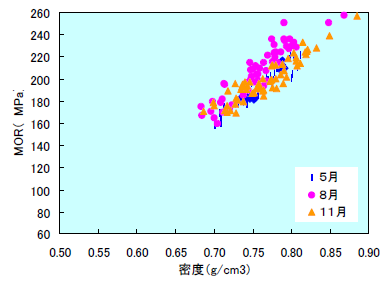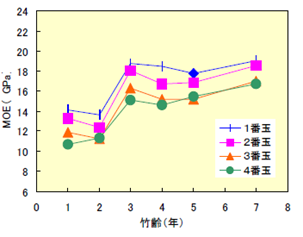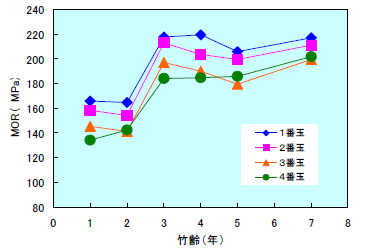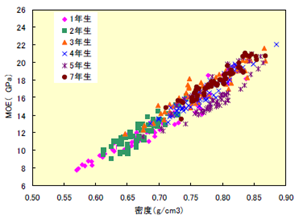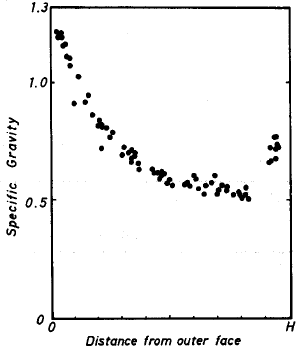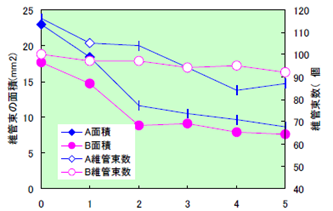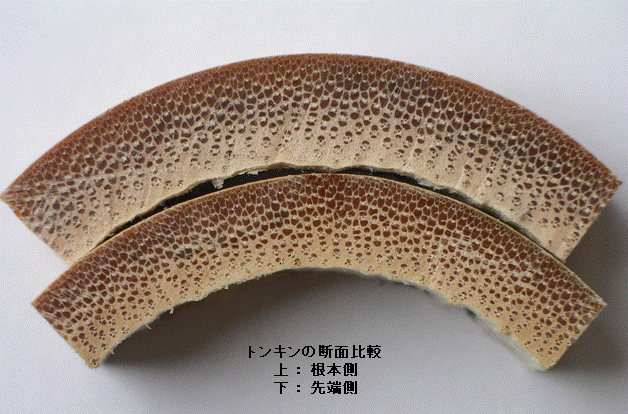| 6-2-1 �|�̓����@1 |
�H����
�|�̔M�����i�Γ���j�ɂ��āA�ފƂɊւ��鏑�ЁE�����EWeb
Site�ׂĂ���ʓI�ȃf�[�^��
�قƂ�ǂ���܂���B
�����ŁA�ފƂƂ͒��ڊW�Ȃ����ЁE�����𒆐S�ɒ|�̐����E���M�������ɂ��Ē��ׂĂ݂܂����B
���|�̔M�����ɂ���
�P�D�������@�Ƃ�
(1)�������₷������B
(2)
�\�ʂ��Y��ɂ��A���܂ł��ۑ��ɂ����čH��ɂ��x�Ⴊ�Ȃ��l����B�@
(3) �Q����J�r��h���B
�@�@
�@�@���߂ɍs�����̂ł���B
�Q�D���߁@(�Ȃ��蒼��)�@�Ƃ�
�@�@�|�̓���x�i70�`90���A�ے|�̏ꍇ�� 90�`125���j�ȏ�ɉ��M���āA�_�炩���Ȃ����Ƃ���ŕȂ��Ƃ邱�ƁB
�@�@���邢�́A�@�ۂ̕��т�^�����ɐL�����Ƃł���B
�@�@�܂��A�Ȃ��蒼���œ����ꏊ�����x�����M����ƏC���ł��Ȃ��Ȃ�̂́A�E�����i��ōd���Ȃ邽�߂ƁA
�@�@�|�����̃w�~�Z�����[�X�E���O�j���̃K���X�]�ړ_*1���㏸�i200���ʁj���A�_�炩���Ȃ��Ȃ�i���邢�́A
�@�@�_�炩���Ȃ�Ȃ��j�ׂƎv����B
�@�@���̗l�ȏ�Ԃŋ����ɋȂ��蒼�����s���ƁA�Y�����n�܂�|���Ƃ��Ȃ��Ă��܂��Ǝv���܂��B
�@�@���������āA�Ȃ��蒼���͒Z���Ԃōs���i���邢�́A���܂艷�x���グ�Ȃ��ōs���j�����K�v�ł��B
�R�D�Γ���@�Ƃ�
�@�@�|�ɂ͎��R���ƌ�����*2�ƌĂ��2��ނ̐������݂��Ă��܂��B
�@�@���R���͊ܐ������@�ۖO�a�_*3(��Q�O��)�ȏ�̍ނ̍זE���o��זE�ǒ��̋ɂ��鐅�ł��B
�@�@�|���������Ă����R���������������ɂ����Ă͎��k���Ȃ����A���x�I�������ω����܂���B
�@�@�Ƃ��낪�A�@�ۖO�a�_�ȉ��Ɋܐ������Ⴍ�Ȃ�ƁA���������������܂��B
�@�@�������͍זE�Ǔ��ɂ����čނ��\�����镪�q�ƓI�Ɍ������Ă��鐅�Ȃ̂ŁA�����������������
�@�@���k����Ɠ����ɋ��x�I�����͑��債�܂��B
�@�@�|���A���鉷�x�Ǝ��x�̊��ɒu�����ƁA�����ꂻ�̊��ƃo�����X���Ƃꂽ�ܐ����ɂȂ�܂��B
�@�@�G�߂�n��ɂ���ĈႢ������܂����A
�@�@���{�̉��O�̕��ϓI�ȕ��t�ܐ���*4�́A���悻�P�T���ƌ����Ă��܂��B
�@�@�܂�A�Γ���Ƃ͉��M���邱�Ƃɂ��A�Z���ԂŃZ�����[�X�̌������������i�E���k��*5�j���邱�Ƃ�
�@�@���x�����߂�Ƌ��ɁA�e��������a�����ɕώ������A�ċz����j�~�����x�i������ԁj���ێ����鎖�ł���B
�@�@�X�ɁA���O�j���i�M�d�����̐ڒ��܂̗l�Ȑ���������j���M�_���d��*6�ŋ��x���X�Ɍ��コ���鎖�B�炵��
�@�@�A���A���M���x�͒�����180���ȏ�ɂ��Ȃ������ǂ������ł���B�i�|�����̃w�~�Z�����[�X����������j
�@�@�܂��A�Ꮌ�x�̊��ɒ����ԕۊǂ���A�Γ���͕K�v�Ȃ������m��܂���B
�@�@�i�����x�̊��ł́A5�N�E�P�O�N�ۊǂ��Ă����x�͏オ��Ȃ��B�E�E�E���E�J�r����Ԃ����j
�@�@��̓I�ȉΓ��ꉷ�x�E���Ԃɂ��ẮA���m�ł͂���܂��A
�@�@���L�̕�������@140���`180���ʁ@�Ł@1���Ԉʁ@���ǂ��炵���B
�ȉ��́A�_���E���Г�����̈��p�f�[�^�ł��i�ꕔ���M�j
���|�̓���
�P�D�|�̐���
|
���� |
wt�� | �@ |
| �Z�����[�X | ��50 | �O���R�[�X�i�u�h�E���j�̒������̂悤�ȕ��q�������W�܂��đ��̂悤�ɂȂ��Ă��� |
| �w�~�Z�����[�X | ��20 | �������ɂ��������̂���Z�����[�X�ƃ��O�j�������т������������ |
| ���O�j�� | ��20 | �זE�ƍזE�̊Ԃɑ����܂܂�A�זE���m���Ȃ�����A�Z�����[�X��⋭���ċ�����_����������� |
| ���̑� | ��10 | ���ށi�f���v���A�V�����Ȃǁj�A�A�~�m�_�ށi�`���V���A�A���j���Ȃǁj�A�N�����t�B���ȂǂŁA�����̏_�זE�ɒ~�ς���� |
| ���ʐ��� | - | �j�A�r���A�m���A�b���A�l���A�e���A�l���@�Ȃ� |
�@���f�̊����@�F�@�Y�f�@��T�O�������A�_�f�@��S�T�������A���f�@��T�������A���f�E�~�l�����ށ@��P������
�Q�D�|�����̔M����
| �@ | �K���X�]�ړ_�i���j | �M�������x�i���j �i�����ɂ��قȂ�j |
||
| ������� | ������� | |||
| �Z�����[�X | �Q�R�P�`�Q�T�R | �Q�R�P�`�Q�T�R | �Q�S�O | 300�`370 |
| �w�~�Z�����[�X | �P�U�V�`�Q�P�V | �T�S�`�P�S�Q | �P�W�O | 190�`480�@�i�L�V�����j |
| ���O�j�� | �P�R�S�`�Q�R�T | �V�V�`�P�Q�W | �S�Q�O | 250�`500 |
�R�D�|�̊ܐ����Ƌ��x
| �@ �}�P�́A�|�̊ܐ����ƙ��f���x�̊W�������Ă��܂��B �@�@�ܐ������@�ۖO�a�_�ȉ��ɂȂ�Ƌ��x�������Ȃ鎖�� �@�@����܂��B �@�@���̐}�́A�Џ@�|�E�^�|�E�W�|�̃f�[�^�ł����A �@�@�g���L���ɂ��K�p�ł���Ǝv���܂��B �@�@���R�����ł͂P�O�����x�ȉ��ɂ͂Ȃ�܂��A �@�@�����܂̓����������e��ɕۊǂ���Ίܐ��� �@�@�P�O���ȉ��ɂ��邱�Ƃ��\�Ǝv���܂��B �Q�l�@�@�M�����؍ނ��P�U�O���ߖT�̉��M�Ə������M�ɂ� �@ |
|
|
�}�P�@�|�̊ܐ����Ƌ��x |
�S�D�|�̔M�������@�Ƌ��x�i�}�_�P�j
| �}�Q�́A�|�̔M�����̕��@�Ƌ��x�̊W�������Ă��܂��B �M�����̈Ⴂ�ɂ�鋭�x�ւ̉e���͂Ȃ���������܂��B �������� �@�@�@4�N����11���ɔ��̂����| �@�@�@�N���F�����������ނ�100�� �@�@�@ (NaOH 0.05�����n�t��20���Ԏϕ�����) �@�@�@�Y���F�����C�����ނ�,�������������{�����|�ނ� �@�@�@ ���͗e�����150���̖O�a�����C �@ �i���́F0.5MPa�j��20���ԔM���� �@ �@ |
|
|
�}�Q�@�|�̔M�����Ƌ��x |
�T�D�|�@�ۂ̑ϔM���i�Џ@�|�j
�i�P�j ���M���x�Əd�ʕێ����̊W �@�@�}�R�́A�@�|�b����������́C�A�|�P�@�ہC�B���o�� ���̔��Ӓ|�̂R�҂̉��M��̏d�ʕێ����������Ă��� ���B�@�ƇB�ł�160������ƌ��ʂ��ڗ��B �@�@����͔M�������x�̒Ⴂ�w�~�Z�����[�X�ɂ����̂� �@�@�l������B �@�@�@ �@�@���������F�P�O�O���`�Q�S�O���܂łQ�O�����������A �@�@�@�@�@�@�@�@�@�e���x�ɂP���ԕ��u��̏d�ʂ𑪒� �@���|�̉Γ��ꉷ�x�́A160�`200���ȉ��ɂ��ׂ����H �@ |
|
|
�}�R�@�|�@�ۂ̉��M���x�Əd�ʕω� |
|
| �i�Q�j
�V�R�@�ہi�|�A���j�̋��x�ƔM�������x�̊W �@�@�@�}�S�ɂ��A�������܂߂���140���ȉ��̒ቷ�� �@�@�@�ł͐��SMPa�ȏ�̍����x�����邪�A �@�@�@�P�S�O�������ɂ��č����ɂȂ�Ƌ��x���}������B �@�@�@�i�������ԁ�1���ԁj �@�@ ���Γ��ꉷ�x�́A150���ȉ��ɂ��ׂ����H �@ �@ �@ |
|
|
�}�S�@�V�R�@�ۂ̉��M���x�Ƌ��x �@ |
|
|
�@�@�@�R�U�O�O�b�i1���ԁj�ȏ�ł͋��x�ω����Ȃ���������
�@ �@ |
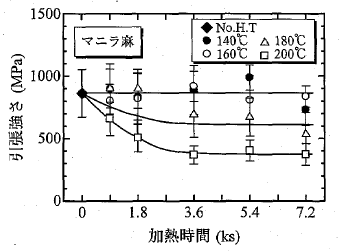 |
|
�}�T�@�V�R�@�ۂ̉��M���ԂƋ��x |
�U�D�@�|�̔M�����Ƌ��x�@�@
|
�i�P�j
�}�_�P�̃z�b�g�v���X���^�|���x�����i���^����10���j |
||
|
|
�@ |
�@ |
| �}�U�|�P�@�Ȃ��e��(MOE)�@ | �}�U�|�Q�@�Ȃ����x(MOR) | �}�U�|�R�@�Ȃ��j�f�Ђ��� |
�i�Q�j�@�}�_�P��p�����o�l�̐��� �@�@�@�}�_�P���|�܂�p�������i�R�C���o�l�j�̐���ɂ����āA�˂̊���莞�Ɩ��Z�̎��� �@�@�@�M�������œK���x�͉�����P�U�O���ł������B�i�����ǂɊ��������^�B���̌�A�����łQ�`�R���j �@�@�@���e������݂�ƂP�U�O�����œK���H |
||
�V�D�|�̔��̎���
| �i�P�j �Q���Ή� �@�@�@10������11���ɔ��̂���̂��ǂ��B �@�@�@���R �F �Q���̉a�ƂȂ铜���̊ܗL�����Ȃ� �@�@�@�@�@�@�@ �ܐ������Ⴂ �@�@�@�@�@�@�@�i⡂̎����́A�����������Ȃ�j �i�Q�j �|���x�Ή� �@�@�@�}�V�́A�͔��̎����ƋȂ����x�iMOR�j�̊W�ł��B �@�@�@4�N���|�ނ̔��̎����i�T�C�W�C�P�P���j�̈Ⴂ�ł����A �@�@�@���̎����͋��x�ɉe�����Ȃ���������܂��B �@�@�@���܂�A���x�Ɋւ��ẮA�����̂��Ă��ǂ��B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�A���A�R�N���ȏ�j |
|
|
�}�V�@�|�̔��̎����Ɩ��x |
�W�D�|�̑I��
|
�i�P�j �|��Ƌ��x�i�}�_�P�j �@�@�@�����b�h����ɂ́A�R�N���ȏ�̒|���K���Ă��� |
 �@�@ �@�@ |
|
�}�W�|�P�@�|��ƋȂ����x�E���x �@ |
|
|
|
|
| �}�W�|�Q�@�|��ƋȂ��e�� | �}�W�|�R�@�|��ƋȂ����x |
�i�Q�j ���x�Ƌ��x�i�}�_�P�j �@�@�@�}�X�|�P�́A�}�_�P�̋Ȃ����x�iMOE�j�ŁA���x�Ɣ��ɋ������̑��ւɂ���A �@�@�@���x�𑪒肷�邱�Ƃɂ���āA�Ȃ����x�𐄒肷�邱�Ƃ��\�ł��邱�Ƃ��킩��B �@�@�@�i���̎����ɂ͉e������Ȃ��E�E�E�}�V�Q�Ɓj �@�@�@�}�X�|�Q�́A�Џ@�|�̒f�ʕ����̖��x���z�ł��B�\�ʑ��̖��x���傫���i���x���傫���j��������܂��B |
|
|
|
|
| �}�X�|�P�@���x�ƋȂ��e���@ | �}�X�|�Q�@�Џ@�|�f�ʂ̖��x���z�@ |
�i�R�j �g�p���ʁi�ԋ�*7�j�Ƌ��x�i�}�_�P�j �@�@�@�}�P�O�ɂ��A���������̕��ʂ̈Ⴂ�ɂ��ۊǑ����y�шۊǑ��ʐς̊W�́A����ɂ����ɏ]�� �@�@�@�ۊǑ����y�шۊǑ��ʐςƂ��������鎖���킩��܂��B �@�@�@�}�P�P�́A�g���L���i3.6m�j�̍��{���Ɛ�[���̒f�ʎʐ^�ł��B�ۊǑ����͔���܂��A��[���̕��� �@�@�@�ۊǑ��������ׂ��Ȃ��Ă��邱�Ƃ�����܂��B �@�@�@�܂�A�|�͍��{������[���̕������x���Ȃ��i�ǂ��Ȃ���j�Ƃ������ł���A�����e�[�p�[�̃��b�h�ł��A �@�@�@���{���������g�p�����ꍇ�Ɛ�[���������g�p�����ꍇ�ł́A��[�������̃��b�h�̕����_�炩�� �@�@�@�i�Ԏ肪�Ⴍ�j�Ȃ��Ă��܂��B�@ |
|
|
|
|
| �}�P�O�@�|�̕��ʁi�ʔԁj�ƈۊǑ� | �}�P�P�@�g���L���̍����Ɛ�[�̒f�� |
�@�@�@�������̍��{�����o�b�g�ɁA�ۊǑ��ׂ̍���[�����e�B�b�v�Ɏg�p���邱�Ƃ͗��ɓK���Ă��� |
|
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
���p��
*1�@�K���X�]�ړ_�Ƃ�
�@�ő̂̌��������M���Ă䂭�ƗZ�_�ʼnt�̂ɕς��n�߁A�ő̂Ɖt�̂���������Ԃ͉��x���Z�_�Ɉێ�����A
�@�ő̂��S�ĉt�̂ɕς��ƁA�܂����̉��x���㏸���Ă䂭�B
�@�����A���̌ő̂����M�����ꍇ�́A�ቷ�ł͌����Ȃ݂Ɍ���(���������傫��)���������Ȃ�����(�S�x��
�@����s�\�ȂقǑ傫������)
�ő̂����鋷�����x�͈͂ŋ}���ɍ����ƔS�x���ቺ���������������B
�@���̂悤�ȉ��x���K���X�]�ړ_�ł���B
*2 �������Ƃ�
�@�זE�Ǔ��ɂ����Ė؍ށi�|�j���\�����镪�q�ƓI�Ɍ������Ă��鐅�̂��ƁB
*3�@�@�ۖO�a�_�Ƃ�
�@���R���������Ȃ�ܐ����̎��B
*4 ���t�ܐ����Ƃ�
�@���R�����ł̊ܐ����̎��B
*5 �k�������E�E���k���Ƃ�
�@2�̊��\��炻�ꂼ��1�������������A���ꂪ�������ď����ȕ��q���`�����ĒE�����A����Ɠ�����2��
�@���\��̎c�����������m�ł��������������ĐV�������\���������`���̔����ł���B
�@�Ⴆ�J���{�L�V�� −COOH
�ƃq�h���L�V�� −OH �̏k�������ł́A�J���{�L�V���
OH�A�q�h���L�V���
�@��H
���������Č����������q���E������B����Ɠ����Ɏc�����J���{�L�V���
−CO �̕����ƃq�h���L�V���
�@ −O
�̕������������ăG�X�e������ −COO− ����������B
�@�k�������̓��A�����q���E������ꍇ���A�E���k���i�����������キ�����j�ƌĂԁB
*6 �d���E�M�_���d���Ƃ�
�@�d���Ƃ́A�ȒP�ȍ\���������q����������ȏ㌋�����ĕ��q�ʂ̑傫�ȕʂ̉����������錻�ۂ�
�@����A��C�̑��݉��ŔM���������Ƃ��ɋN����d��������M�_���d���Ƃ����B
*7 �ԋʂƂ�
�@1�ԋʁC2�ԋʂƂ��A
�@�n�ʂɋ߂�2�C3�ߊԂ͐ߊԂ��Z�������Ђ��쐻�ł��Ȃ����ߐ�̂��A���̏㕔����3�ߊԂÂ�4�{�ɋʐ�
�@�肵�A��������1�ԋʁA2�ԋʁA3�ԋʁA4�ԋʂƂ����B
*8 MOE�CMOR�Ƃ�
�@MOE�����MOR�́A���ꂼ��Modulus of Elasticity�����Modulus of
Rupture�̗���ŁA�e��������ыȂ��j
�@��W���̂��Ƃł��B
�@�e�����͍ޗ��̕ό`�̂��ɂ�����\���l�ŁA���́|�Ђ��Ȑ��ɂ����āA�Ђ��݂̏������Ƃ���ɂ����钼��
�@�̈�ł̌��z�ɑ������܂��B�e���W���Ƃ������܂��B
�@�Ȃ��j��W���́A�Ȃ����x���邢�͋Ȃ������Ƃ��Ă�A�ޗ��̋��x��\���A�Ȃ��d���Ĕj����
�@�̉��͂ɂ�����܂��B
�@�ό`���ɂ����ޗ��́A�����Ǝv���邩���m��܂��A�Ⴆ�K���X�̂悤��MOE���傫���Ă�MOR�͏���
�@���A���Ȃ킿�Ƃ��ޗ�������܂��B���̓_�Ɋւ��āA�؍ނł͈�ʂɋȂ��e�����A�Ȃ����x�Ƃ��ɔ�d�̑���
�@�ɔ����đ��傷�邽�߁A�Ȃ��e�����ƋȂ����x�̊ԂɗǍD�Ȑ��̑��֊W�����݂��܂��B
�����p�E�Q�l����
�_��
�@�@�@�ے|�ނ̋Ȃ����H�y�ѐڍ��Z�p�Ɋւ��錤���@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ʕ{�Y�ƍH�|�������@�@���|
�Ĉ�@,��
�@�@�@�|�ނ̐����Ɋւ��錤��(��13��)�@�|�ނ̙��f���x�Ɗܐ����Ƃ̊W�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��B��w�_�w���@�@���c�@��
�@�@�@�|�@�ۂ̓����Ƃ��̗p�r�J���ɂ��ā@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����s���Y�ƋZ�p�����Z���^�[�����C��3
���C2008 �N�@�@�r�c �P���@,��
�@�@�@�@�\���O���[���R���|�W�b�g�̊J���Ƃ��̕]�����@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@������w��w�@�\�V�I�e�N�m�T�C�G���X�������@����
��
�@�@�@���k���^�ɂ��}�_�P�̋@�B�I�����̌���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@������w��w�@�\�V�I�e�N�m�T�C�G���X�������@����
��
�@�@�@����|�ѓ��ɂ�����|�ނ̋Ȃ����x�����ɂ���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�啪���|�H�|�E�P���x���Z���^�[
�@��� ���i�@,��
�@�@�@�|�܂�p�����˂̐���Ǝ���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����w����w���I�v.
���ȋ���@�x�R �N�V
�@�@�@���E�\�E�`�N�̋��x���\�F�b�Ǔ��̃����O�W�����z�ɂ���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�k�C����{�_�{���@�@��c
�P�i
�����o�莑��
�@�@���������̏������@�y�я����V�X�e��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@http://www.j-tokkyo.com/2001/B09C/JP2001-079537.shtml
�@�@�@�Z�����[�X�n�ޗ������|���E���^�������g�����̐������@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@http://www.patentjp.com/12/L/L101703/DA10001.html
�@�@�@�Z�����[�X�G�X�e��������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@http://patent.astamuse.com/ja/granted/JP/No/3970947/%E8%A9%B3%E7%B4%B0
���Ё@
�@�@�@�n�X��
�u�|�̖��͂Ɗ��p�v�@�|�������p�t�H�[�����@����
�x�O�@��
�@�@�@�u�k�� BULE BACKS
�u���̂Ȃ�ł������T�v�@���̔����ف@��
WEB SITE�@
�@�@�@�]�˘a�Ƃ��ł���܂Ł@http://members2.jcom.home.ne.jp/kuniichi/seisaku.html
�@�@�@�p���j�̔ȂŁ@�@�@�@�@�@�@http://haruworks.exblog.jp/12670940/
�@�@�@���̒��ɂ��鐅�@�@�@�@�@http://www.ohi-s.co.jp/PDF/kanso1.pdf
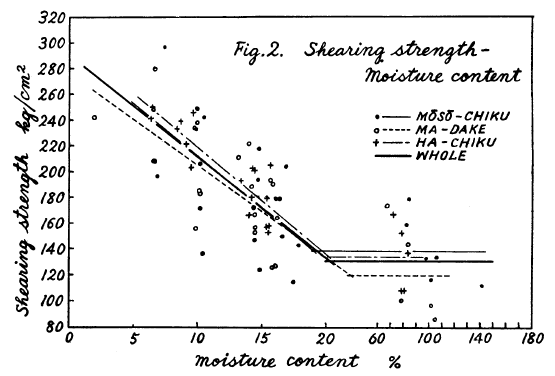
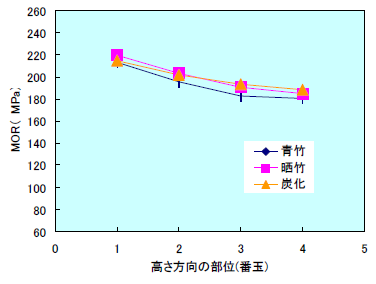

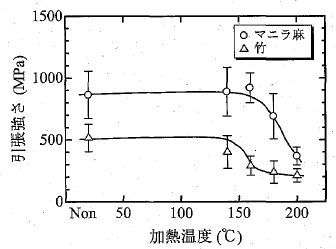
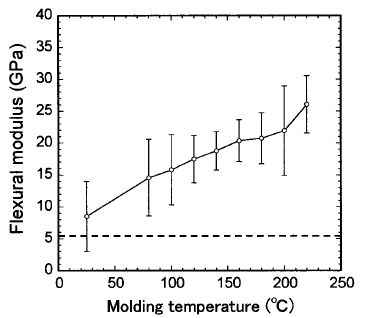 �@�@
�@�@